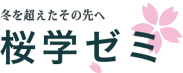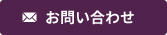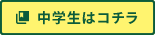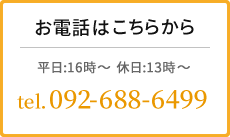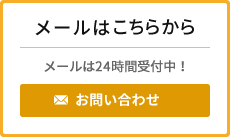ポイント
難関大学の中では、簡単な教科が多いのが九州大学の特徴です。そのため、基礎をしっかりと固めて、みんなが解ける問題を落としてはいけません。その上で、理解していなければいけないものから、論理的に答えを導く力をつけていきます。合否をわけるのは、数学と英語(一部、社会と国語と生物)で部分点を積み重ねていくことです。
センター試験と二次試験のバランスを取る

九州大学を受ける上で最も大切なことは、センター試験と二次試験のバランスを取っていくことです。傾向と対策は前期試験を前提としているので、後期試験の場合は試験科目が異なったり、配点が異なったりすることがあります。
東大や京大に比べて、センター試験の割合が高くなっています。そのため、センター試験で変な点数を取ってしまうと、二次試験での逆転が難しくなってきます。しっかりとセンター試験の対策と二次試験の対策のバランスを取っていく必要があります。
バランスを取って勉強をするためには、高3になる前に、入試問題に少し触れておくことです。理系であれば文系用の数学、文系であれば国語の記述対策はやっておくべきでしょう。高3の夏休み以降はセンター試験対策に時間を取られることが多くなってしまいます。そのため、二次試験の対策は一度触れてから高3に入った方が無難です。
では、教科ごとでどのような傾向があり、どのような対策を行っていくべきかを紹介していきます。そしてそのあとに、特に傾向が異なる学部の特徴をまとめていきます。
九州大学における教科ごとの傾向と対策
【英語】レベルは簡単!英作文が勝負の分かれ目

九大は、他の難関大学に比べて英語が簡単です。得点源が決まっていない場合は、英語を得点源にしてくのがいいと思います。難しい単語を連発されることもないため、しっかりとした英語力さえあれば、高得点を取ることも難しくありません。
得点を伸ばしていく上で大切な対策は、英作文にかける時間です。九大の場合、ちょっと分量のある英作文が出題されます。和文英訳も含めると、英語を各分量が多くあります。
特に英作文では、ただ英語を書くだけではなく、自分の意見や、その理由を書かなければいけない場合がほとんどです。そのため、自分の意見などを書くのに時間がかかる場合は、しっかりと対策をしていく必要があります。ここに時間をかけてしまうと、他の問題の時間が圧迫されるため、できるだけ多くの対策をしておきましょう。
勉強方法としては、小論文などで出題されるようなテーマに関して、ある程度答えを用意しておき、英語で書く練習をしておくことです。英文を書いてみて、英語の先生の添削をうけてください。文法の微妙な意味の違い(完了形か?過去形か?など)を抑えて行ってください。
【数学】問題文に隠された流れを見つける
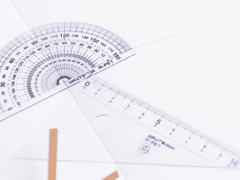
数学の出題は、「関数」「図形」の出題率がほぼ100%になっています。確率の問題も多く出題されています。以下の対策は最優先で行ってください。
- 基本的な微分、積分の解き方を確認
- 図形問題を「図形として解く」「ベクトルとして解く」の2種類で解く
- nを使った確率漸化式を作る練習
- 基本的な解き方をすべて復習する
- 記述形式で絶対に抜かしてはいけない説明を把握する
数学の問題としては難しくなく、オーソドックスな問題が半分ほどです。そこで点数を落とすことはできません。大問の中で2問くらいは、8割以上を狙っていきたいです。その上で、部分点を積み重ねる技術を身に着けてください。
九大に限ったことでありませんが、数学の問題を解くコツは、問題文に隠された流れを見つけることです。特に大問に対して、(1)~(3)などの小問がある場合には、この流れを見つけることが最重要になります。 部分点を積み重ねるコツは、流れに乗りながら問題を解いていくことです。大きく流れに逆らわなければ、最後の答えまで行きつかなくても、多くの部分点を稼ぐことができます。
数学は(1)が次の問題へと繋がっていきます。なぜ、さっきその式を計算させられたのか、出題側の意図を読み取っていく訓練をしてください。
【理科・社会】中途半端に暗記をせずに理解をする。読解力がポイント。

理系では理科、文学部では社会があります。この二つはただ覚えているだけでは意味がありません。しっかりと本質を理解していなければ問題が解けません。
そして、理解と知識を使い、問題文を読んでいく必要があります。問題文では、今まで見たことない反応や資料などが出題されることがあります。しかし、そういった問題は、今までの基礎的な知識に加えて読解力が必要になります。
問題文を読んで、情報を受け取りながら、従来の知識と照らし合わせて問題を解いていく訓練をしなければいけません。今まで習ったことだけを解いていればいいわけではありません。試験本番でも勉強をするときのように、新しいものを理解して、解答につなげていく能力が必要になるので、そういった練習問題を解いて慣れていく必要があります。
【国語】本文の言葉を駆使して解答を書いていく
九大の国語も、他の難関大学に比べれば問題文はそこまで難しくはありません。しかし、特に現代文などでは高度な内容の文章が出題されることが多くあります。内容的に難しいので、他の教科で取ろうと思ってしまう高校生もいますが、しっかりと対策をすればできない問題ではありません。
国語の対策は、問題集や赤本の解答にあるようなきれいな言葉を目指してはダメです。むしろ、解説に書いてあるどうやってその答えが出来上がったのか?を重視してください。その上で、綺麗な言葉ではなく、本文の言葉をつなぎ合わせながら解答を書く訓練をしてください。本文の構成を理解したうえで、本文の言葉をうまくつなぎあわせながら解答を書くことが高得点を目指す近道です。
受験をするうえで気を付けておきたい学部
センター試験と二次試験の配分一覧
|
学部 |
センター試験 |
二次試験 |
|---|---|---|
|
文学部 |
33% |
67% |
|
教育学部 |
43% |
57% |
|
法学部 |
33% |
67% |
|
経済学部(経済・経営) |
43% |
57% |
|
経済学部(経済工学) |
37% |
63% |
|
理学部 |
39% |
61% |
|
医学部(医学) |
39% |
61% |
|
医学部(放射線・検査) |
39% |
61% |
|
医学部(生命科学) |
36% |
64% |
|
医学部(看護) |
53% |
47% |
|
歯学部 |
39% |
61% |
|
薬学部 |
39% |
61% |
|
工学部 |
39% |
61% |
|
芸術工学部 |
42% |
58% |
|
農学部 |
37% |
63% |
|
共創学部 |
33% |
67% |
【医学部(看護)】センター試験が勝負!

九大の中で、唯一、センター試験の割合が二次試験より高い学部です。センター試験と英語だけで相当な割合を占めています。そのため、センター試験の対策に重点を置いてください。
センター試験の自己採点の結果が足りないようであれば、他の大学に出願を変更することも考慮に入れた方がいいと思います。二次試験の配点の半分は英語です。そして、九大では英語が簡単なため、二次試験では点差が付きにくくなっています。しっかりとセンター試験で点数を稼いでリードすることが定石です。
【共創学部】小論文対策は高2までに!
九大の中でも異質な学部です。前期試験で小論文があります。内容は文系でも理系でも関係のないものが出題される傾向にあります。日ごろから、様々な問題に対して、自分の意見を書く練習をしておく必要があります。
小論文の対策は
- 何度も自分で文章を書いてみる
- 様々な社会問題に関する情報を集めておく
小論文は付け焼刃で対策ができるものではありません。文章は何度も書いてみなければうまくなりません。インプットばかりでは役に立ちません。特に共創学部の場合はAO入試で合格した高校生もいますが、彼らはセンター試験などの学力は一切見られずに、小論文やその中に登場する英語だけで判断されています。
ここで一番判断されていることは、自分の考えていることを論理的に説明できるかどうかです。ただ主張をするだけでなく、自分の考えを段階的に分析し、情報を入れながら相手を説得していく力です。